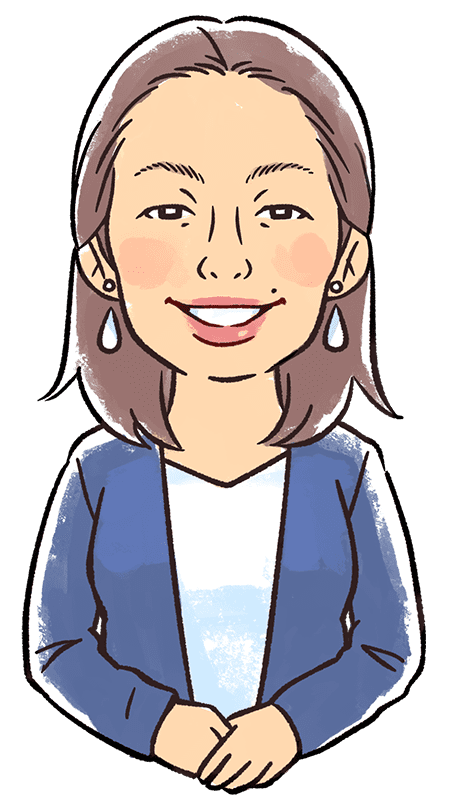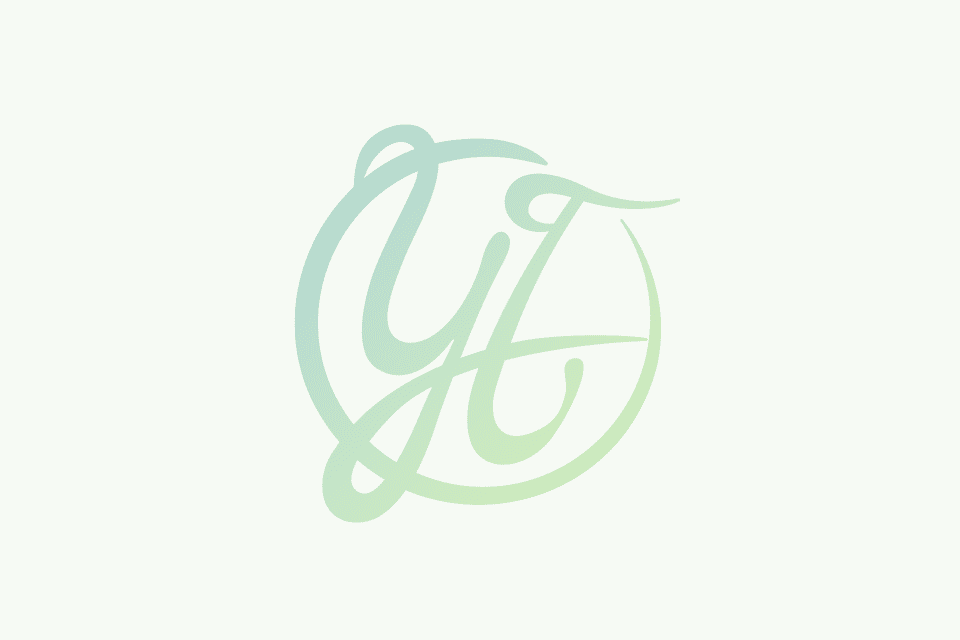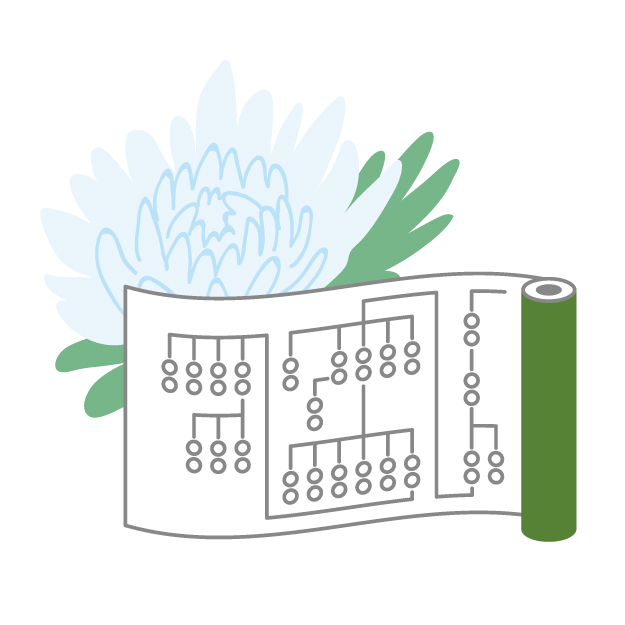あさのあつこさん著「闇医者おゑん秘録帖」シリーズはやっぱり面白い
〈医療〉時代小説傑作選「いやし」をきっかけに、あさのあつこさん「闇医者おゑん秘録帖」シリーズを知り、全部読みました。(といっても2巻のみ。)
第1巻「闇医者おゑん秘録帖」は2013年、
第2巻「闇医者おゑん秘録帖 花冷えて」は2016年に出版されています。
江戸時代、竹林に囲まれたしもた屋で子堕ろし(中絶)を行う「闇医者」おゑんのお話です。
最高におもしろい!
人の狡さ、嫌らしさ、傲慢さ、弱さ、が知れます。
誠実で、寛大で、謙虚で、強い人に憧れますが、そうとばかりはいかないのが人間。
あさのさんの作品は(時代小説しか知りませんが)、ひとりの人間の中にある、汚い部分と綺麗な部分、弱い部分と強い部分の共存が巧みに描かれており、ものすごく引き込まれます。
主人公おゑんの言葉で心に残っているものを紹介します。
おゑんの心に残るセリフ
光が正しく闇が禍々しいと誰が決めたのか。いつの世にも、光と闇は混在して生きていた。どちらも等しく必要なのだ。
第1巻「春の夢」より
明るくて幸せそうに見える人でも「闇」の部分は必ずあるし、
逆に「闇」を抱えている人であっても、必ずどこかに「光」はある。
光だけの人、闇だけの人、なんていないことを理解して、ほんの一面だけで人を判断しないようにしたいものです。(もちろん自分のことも。)
言葉には外に出すべきものと、内に秘めたままにしておくべきものと二通りがあるのだそうです。秘めておくべきものを外に出せば禍となり、外に出すべきものを秘めておくと腐ります。
第1巻「冬木立ち」より
大人ですから、なんでもかんでも口に出すことは良くないというのは分かります。
でも、「外に出すべきものを秘めておくと腐る」という感覚は持っていませんでした。
なるほど。吐き出さなければいけない感情もあるんだ、と納得です。
しゃべってしゃべって、しゃべり終えてふと気が付くと脚に力がよみがえっていた。荷が軽くなったわけではない。現の何が変わったわけではない。でも、その荷を背負って立ち上がる力が脚と心に芽生えている。
第1巻「冬木立ち」より
悩みや愚痴を口に出したところで現実は何も変わらない。
でも、外で出すことで心が軽くなることは確かにあります。
心が軽くなる感じを、あさのさんは「その荷を背負って立ち上がる力が脚と心に芽生えている。」と表現する。
この表現の仕方がすごく好きです。
心を潰さないために、適度に吐き出し、その荷を背負えるだけの気力を芽生えさせる。
忘れないようにしたいです。
お春の疼きはお春のものだ。耐えて、凌いで、傷の上に瘡蓋を作るしかない。お春にしか癒せないものなのだ。
第2巻「竹が鳴く」より
あさのさんは別のインタビューでも「瘡蓋」について語っている場面があります。
「傷ができて瘡蓋ができた皮膚は、傷のない皮膚より強い。何度も何度も痛みを味わった人は、痛みに鈍感になるのではなく、痛みに対して強くなる。」とおっしゃっていました。
確かに。瘡蓋のないきれいな心より、傷のいっぱいある心の方が強い、そして美しい、とわたしも思います。
なぜに女はこうも、己に罪を押し付け、己で己の心を削ろうとするのか。苛立ちすら覚える。
第2巻「竹が鳴く」より
女性に限らず日本人は「わたしなんて」と、なりがちです。
自分を守るため、ひいては周りの皆を守るため、自分を認めること、褒めることを忘れないようにしたいです。
泣くことができれば、涙を流せれば、人はどうにか生きていける。辛さを悲しみを嘆きをずるずると引き摺りながらも、前に進める。 傷は癒えない。しかし、人は恢復する。生き残った者は生き続けるしかないのだ。だから、恢復する。決して癒えない傷を抱きつつ、恢復していくのだ。
第2巻「花冷えて」より
傷は癒えないけど、人は恢復していける生き物だと。
辛さや悲しみを経験して、涙を流して、そして恢復することで人は豊かになれる。
心強い言葉です。
まとめ
あさのさんの作品を読むと、自分の中にある嫌な部分も別にそのままでもいいのかも、と思えます。
妬み、嫉み、鬱屈したもの、などいわゆる「負」の感情を押さえつけることなく、それも自分だとまるごと認めて生きていくことができれば、とても生きやすいのかもしれない、と感じます。
作中の登場人物のひとりのセリフで「世の中、一言で片づけられるような人はいません。」というものがあります。
そうなんですよね、皆、色んな面を持っているんですよね。
わたしはきっと、前向きで真面目な人でありつつ、臆病で傲慢で暗い人でもある。
それでいいのかな、だからおもしろいのかな、なんて思います。